今回は簿記って何なの?実際難しい?理系じゃないとムリ?などの疑問に答えていきながら簿記について解説していきます。
1.簿記とは?

「簿記」という言葉を聞いたことはあるけど、実際に何するものなのかよくわからない…という人、多いですよね。実際に私も勉強する前は、「企業の経理の人が使う専門知識?」くらいの認識しかありませんでした。ですが、簿記は思ったよりも身近で、基本を知るだけでもお金の流れがよくわかるようになります!
ズバリ!「簿記」とは、お金の流れを記録・整理してすることです!
企業は色んな会社との取引や商品の販売だったり、お金の移動をわかりやすく記録するものが「簿記」になります。
企業の経理だけでなく、個人の家計管理や投資にも役立つ知識なので、簿記を学べばお金の流れがわかるのに加えて、会社の財務状況を把握できるようになります。
たとえば、ケーキ屋さんがケーキを作るための材料を買いました。このときお金を払って材料を手に入れたので、「材料を1000円買った(費用)」と記録します。では次に、ケーキをお客さんに2000円売ったとします。すると記録では、「ケーキを2000円売った(収益)」となります。これらの取引を仕訳という作業で記録していきます。
2.簿記検定の種類とは?日商簿記・全経簿記・全商簿記の違いとは?
さて、次は簿記の種類について見ていきましょう。簿記の資格にはいくつか種類がありますが、一番有名なのが「日商簿記」です。世間の人が言っている簿記がこれに当たります。
他にも、学校教育向けや業界特化型の簿記検定があります。それぞれの特徴を紹介します。
- 日商簿記
日商簿記は日本商工会議所と各地商の工会議所が主催する簿記に関する検定試験です。最も知名度が高く、企業の経理や会計業務で広く活用され、就活に有利な資格になります。難易度順に1級・2級・3級・簿記初級があります。
詳細についてはこちらの商工会議所公式ページで確認できます。
- 全経簿記
全経簿記は全国経理教育協会による検定試験です。経理や会計の専門学校生を対象としているため、主に学生が受験します。日商簿記の難易度に比べて低め、上級・1級・2級・3級・基礎簿記会計という5つのランクがあります。
- 全商簿記
全商簿記は、全国商業高等学校協会が主催する検定試験です。商業高校や商業に関する学科を設置している高校で学ぶ高校生を対象としており、1級、2級、3級に分かれています。
3.日商簿記3級・2級・1級の難易度や勉強時間は?
次に、日商簿記のレベル別で難易度を詳しく見ていきましょう!(簿記初級は省きます)
| 級別 | 概要 | 難易度・勉強時間 |
| 3級 | 商業簿記の基礎知識が求められます。仕訳、帳簿の記帳、財務諸表などを学び、初心者向け | 合格率40%~50%前後 80~100時間(1、2か月程度) |
| 2級 | 3級の発展+工業簿記が追加(製造業の原価計算・中小企業の経理業務レベル) | 合格率30%~40% 200~300時間(2~4か月程) |
| 1級 | 会計学・原価計算を含む難関資格(合格で税理士試験の受験資格を取得) | 合格率10%前後 600時間前後(6か月~1年程) |
大学生であれば、3級から始めて2級まで取得するのが理想的です!就活や仕事に役立つだけでなく、さらにはお金の流れを理解できるようになるので、将来にも役立ちますよ😎
4.簿記において「仕訳」とは?
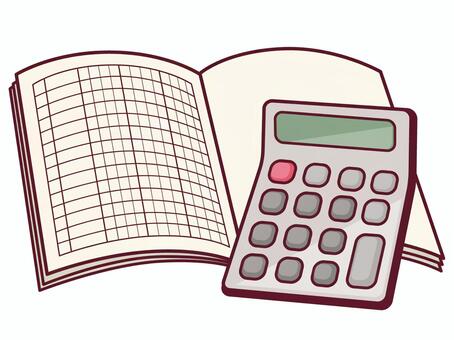
次は「仕訳」について解説していきます!
先ほどちょろっと「仕訳」という言葉を使いましたが、簿記での記録でとても大事なものになります。
「仕訳」とは取引を「借方(左)」と「貸方(右)」に分けて記録することです。借・貸という言葉ですが、「借りる・貸す」みたいなイメージとはちょっと違うので注意してください!
基本的には、「増えたもの」や「使ったもの」は借方(左)、「減ったもの」や「得た原因」は貸方(右)に書くルールになっています。
それを踏まえてさっき例に出したケーキ屋の取引の仕訳を見てみましょう。
・ケーキ屋が材料を1000円払って買いました。(現金払い)
この場合、材料を購入したので材料が増え、購入のため現金を支払ったので現金が減少しました。
つまり増えた材料については借方(左)に、減ってしまった現金については貸方(右)に書いていきます!「仕入」と「現金」という勘定科目を使って表しますと、
(借方)仕入 1,000|(貸方)現金1,000 となります。
勘定科目とは仕訳で記入する「増えた or 減った原因」のことです。これは仕訳によって違う勘定科目を使うので、試験のために覚えなくてはいけませんがそこまで多くないので心配しなくて大丈夫です!
練習していけばすぐ覚えられます👍
仕訳の重要ポイントは(借方)と(貸方)の数は必ず一致し、何が増えて何が減ったかを記録するというところです。
次は売った時の仕訳を見てみましょう!
・ケーキ屋がケーキを2000円売りました。(現金払い)
今回はケーキを売ったことでケーキ屋の収益が増え、現金も増加しました。どっちが借方・貸方かわからなくなりそうですが、収益が出たときはこの形っていうのがあります。
現金が増加したのでその仕訳は借方(左)に、増加の原因となった収益については貸方(右)に記入します。この時の仕訳は…
(借方)現金 2,000|(貸方)収益2,000 こんな感じになります!「なんで現金が右だったり左だったりするの?」という疑問も浮かぶと思いますが、仕訳はすべて形が決まっているのでそこまで難しく考えなくて大丈夫です!
あくまで増えた・減ったは基本ルール的なもので、深く考えなくても形を知っていれば楽勝です!
私も途中から増えた・減ったが曖昧になってしまいましたが、練習していくうちに形を覚えたのでそこまで苦労しませんでした!
実際にこのように記録するのが試験に出てくるので、練習あるのみです📖✏️
5.文系でも大丈夫!簿記はルールを覚えるだけ
ここまで見ると、数字が出てきて「数学や論理が得意な理系向けじゃないの?」と思うかもしれませんが、実際は全くそんなことありません!
私自身、文系学部に所属しており、理系ではない私でも独学で簿記3級では75点、簿記2級では90点で合格することができました。
簿記は数字の計算や仕訳のルールを覚える必要はありますが、決まったルールに従って記録するものなので、ひたむきにコツを掴めば誰でも理解可能な内容です。
加えて数字の計算も高校数学のような問題ではなく、単純なものが多いです。また電卓を使うので計算に弱くても全く心配いりません。
最初は難しく感じるかもしれませんが、基本的な考え方や仕組みを学べば、だんだん慣れてきて「あれ?そんなにかも」と思うようになります。なので、理系でなければ無理だと諦める必要は一切ありません!将来のキャリアアップに活用できるスキルになると思うので、これを機にチャレンジしましょう‼
まとめ
今回は簿記について解説していきました。最後に簡単に振り返ってみましょう。
✅「簿記」とは取引間でのお金の流れを記録・整理すること
✅「簿記」には日商簿記、全経簿記、全商簿記の3種類があり、日商簿記が一般的
✅「仕訳」とは取引を(借方)と(貸方)に分けて記録することで増減を考えなければならない
✅「簿記」は形が決まっているのでルールを覚えるだけ
✅文系でも大丈夫!理系である必要なし!
こちらの記事もおすすめ!
📌独学でらくらく合格!簿記3級のおすすめテキストと私の最強勉強法を伝授
📌忙しい大学生必見!簿記3級合格までの最短スケジュールの立て方
📌【必見】大学生が簿記2・3級を取得するメリットとは?就活で周りと差をつけよう!
簿記検定の最新情報は、日本商工会議所の公式ホームページでチェックできます。
このサイトでは大学生向けの簿記に関する情報を随時発信中です!実務でも活かせる簿記2級・3級の知識を解説しています。さらに勉強法やおすすめ参考書、効率的なスケジュール管理のコツも紹介中です!

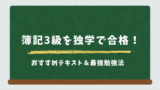

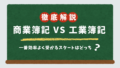
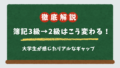

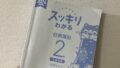



コメント