簿記3級の試験では、仕訳問題が必ず出題されます。しかし、初学者の大学生にとって(借方)と(貸方)の感覚が難しい場合が多いです。
ここでは、簿記3級の試験で間違えやすい仕訳問題をピックアップし、紹介していきます。間違えやすいポイントを押さえて、試験で自信を持てるようにしていきましょう!
よくある間違えやすい仕訳問題
1.現金過不足
「金庫に50,000入っていると思ったのに、実際に確認すると40,000円しか入ってなかった…」
簿記的に言い方を変えると、帳簿上の現金残高は50,000円、実際の現金残高は40,000と額が一致しない。この場合その差額分を「現金過不足」という勘定科目を使って記載します。
ここで大事なことは簿記には真実を記録しなくてはならないということです。
先ほどの例を見てみましょう。
現金不足時は、借方に「現金過不足」を使い、貸方に「現金」を使います。
すると次のようになります。
(借方)現金過不足 10,000 / (貸方)現金 10,000現金を正しい方に合わせなければならないので、現金10,000を減少させます。
その後、この現金過不足の原因が通信費だと判明したとすると、
(借方)通信費 10,000 / (貸方)現金過不足 10,000のようになります。もし原因が判明しない場合は「雑損」という勘定科目を使って相殺します。
現金が過剰に金庫にあった場合は逆の仕訳を行えばOKです。こちらも原因が判明しなかった場合は、「雑益」という勘定科目を用います。
2.他人振出小切手
他人振出小切手とは、相手が振り出した小切手です。これは勘定科目「現金」を使う点に注意です!
自己振出小切手の場合は「当座預金」という勘定科目を用いるのですが、ついうっかりして「現金」ではなく「当座預金」を使って仕訳してしまうことはよくある話です。
それが理解できてれば仕訳自体は大したことありません。
例えば、A社から小切手1,000円を受け取った場合
(借方)現金 1,000 / (貸方)売上 1,000このようになります。
他人振出の小切手の場合は「現金」!これだけ押さえておきましょう。
3.電子記録債務・債権
電子記録債務・債権とは、現金や手形など物理的な物でなく、デジタル化された取引システムを活用するものです。
特に買掛金・売掛金と設定していたものを電子支払いに変更する問題が多いです。
例:A社から商品10,000円を仕入れ、代金を掛けとした。
(借方)仕入 10,000 / (貸方)買掛金 10,000その後、A社に対する買掛金について、電子記録機関に債務発生の記録を行った。
(借方)買掛金 10,000 / (貸方)電子記録債務 10,000このようになります。「売掛金」を電子にする取引はこの逆をやればいいのですが、どっちが債務で債権か混合しないように注意しましょう。
4.未払金・未収入金

商品でお金を払っていない or お金をもらっていない場合、「買掛金」と「売掛金」を使いますが、商品以外でお金を支払っていない or お金をもらっていないときに、「未払金」と「未収入金」という勘定科目を使います。
例:100,000で土地を買って未払いの場合
(借方)土地 100,000 / (貸方)未払金 100,000になります。未払金は負債として計上します。
5.仮払金・仮受金
「仮払金」はとりあえず受けとったお金、「仮受金」はとりあえずもらったお金のことです。
こちらも例を使って考えていきましょう。
原因不明の現金1,000円を受けとった場合、次のようになります。
(借方)現金 1,000 / (貸方)仮受金 1,000「仮払金」と「仮受金」は一時的なものなので、あとで必ず消すものになります。
先ほど説明した「現金過不足」と同じようなものです。
6.立替金・預り金

立替金と預り金は混合しやすいので注意しましょう!
「立替金」は他人のために代わりに払っておいたもの、「預り金」は従業員負担の税金などを預かりあとで国に納めるものです。
「立替金」は従業員のために支払う「従業員立替金」があり、「預り金」は社会保険料や所得税の支払いで従業員の給料から引かれるケースが多いのでしっかり区別しておきましょう!
7.経過勘定(前払・前受、未払・未収の費用や収益)
「経過勘定」という一番だるい勘定科目があります。
これは支払いや収入の取引が発生した期間とその決算期との間にズレが生じる場合に使うものです。
経過勘定には「前払費用」「前受収益」「未払費用」「未収収益」の4つがあり、「お金の動きよりもサービスの提供時期を基準に考える」ことが大切です。一つずつ見ていきましょう。
・前払費用
提供されていないサービスを前もって払ったのが「前払費用」になります。
例えば、保険料や賃貸料を前払いした際に発生します。支払いは完了してますが、その段階では、サービスを受ける権利があるだけなので資産とします。後日サービスの提供を受け、消費してから費用になります。
例:1年半分の家賃を前払い
(借方)支払家賃(費用) 180 / (貸方)現金 180この段階ではすべて支払家賃(費用)にしておきます。その後1年経過し決算になり、半年分の家賃が残っています。
(借方)前払家賃(資産) 60 / (貸方)支払家賃(費用) 60この60はこの先半年借りる権利です。一方、支払家賃の方は180‐60=120がこの1年借りていた費用になります。
・前受収益
提供していないサービスの支払いを前もって受け取ったのが「前受収益」です。
さっき「前払金」の計上の説明をしましたが、相手方がこの「前受収益」になります。
こっちは代金を受け取ったので収益に計上されていますが、サービスの提供を行っていない分は収益に計上できません。そのため収益を減らしていきます。
(借方)受取家賃(収益) 60 / (貸方)前受家賃(負債) 60・未払費用
サービスを受けたけど、まだ支払ってないのが「未払費用」です。
これは4.未払金と混合しやすいので注意!
従業員に働いてもらったけど、給料の支払いがまだ行われていない場合で見てみましょう。
例:2月分の給料を3月に払う場合
・2月末時点(給料払ってないけど従業員は2月に働いた。)
(借方)給料 10,000 / (貸方)未払給料 10,000・3月に実際に支払ったとき
(借方)未払給料 10,000 / (貸方)現金 10,000ポイント:「未払費用」はサービス(労働)の提供は終わってるのに、支払いがあとになるケース!
・未収収益
サービス提供したけど、お金は後でもらうのが「未収収益」です。
これは「後でもらう」イメージです。未収入金と間違えないように!
例:貸してるオフィスの2月分の家賃を3月にもらう場合
会社がビルの一部を貸していて、家賃を翌月払いにしているとします。
・2月末時点(部屋は貸したけど家賃まだもらってない)
(借方)未収収益 10,000 / (貸方)受取家賃 10,000・3月に実際に家賃をもらったとき
(借方)現金 10,000 / (貸方)未収収益 10,000ポイント:「未収収益」はすでにサービス(部屋を貸すこと)を提供済みだけど、お金をもらうのは後というケース!
間違えたときの勉強法
簿記3級では、仕訳を確実にこなすことが求められます。よくある間違いポイントを押さえて、しっかり勉強していきましょう。繰り返し問題を解き、理解を深めることが重要です。
1.まずは解説を見ずに考える
間違えたときはいきなり解説を確認するのではなく、「なぜ間違えたのか?」を考えてみましょう!
勘定科目の意味や仕訳のルールを振り返ると、よりミスを減らせるようにもなりますし、しっかり理解できるようになります。
2.間違えた仕訳は繰り返しやりなおす
やはり何度も解かないと記憶に定着しません。私の場合、間違えた問題は写真を撮っておいていつでも確認できるようにしていました。スマホのメモ機能にまとめておくのも良いかもしれません。
3.パターンを意識する
たくさん問題を解いていくと「あれ?この問題どっかで似たようなの見たな…」みたいなことが多くなってきます。これは簿記の問題には一定のパターンがあり、それを意識できるようになってきた証拠です。
まずは自分が持っている参考書の仕訳を完璧にできるようにしましょう。その後、いろんな問題を解きながら、「この問題は前に解いたあの問題と似てるな」と結びつけて考えることで、応用力が身に付いていきます。
簿記の試験では、全く新しい問題が出ることはほとんどありません。過去に出題された、解いたパターンをしっかり押さえれば本番も焦らず解答できます!
おすすめテキストについては以下で紹介しています。
また簿記検定の最新情報は、日本商工会議所の公式ホームページでチェックできます。
このサイトでは大学生向けの簿記に関する情報を随時発信中です!実務でも活かせる簿記2級・3級の知識を解説しています。さらに勉強法やおすすめ参考書、効率的なスケジュール管理のコツも紹介中です!
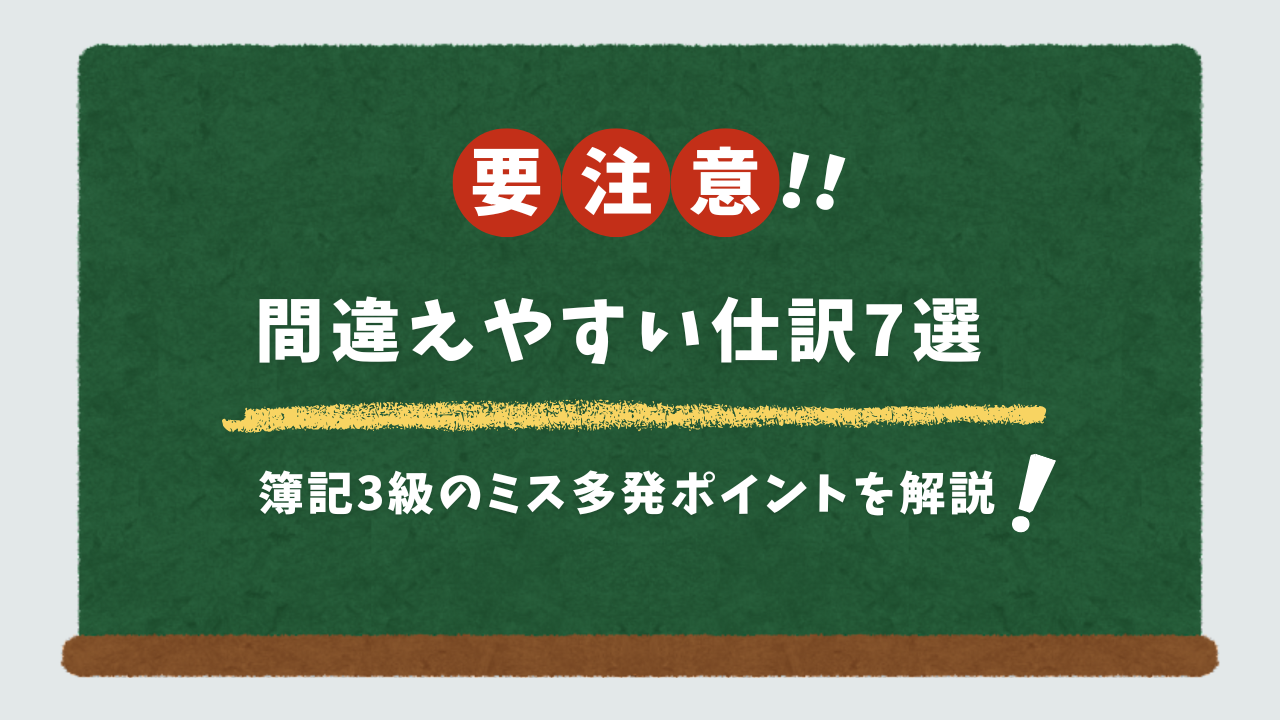
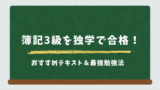

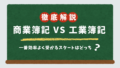
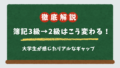

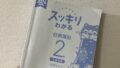



コメント